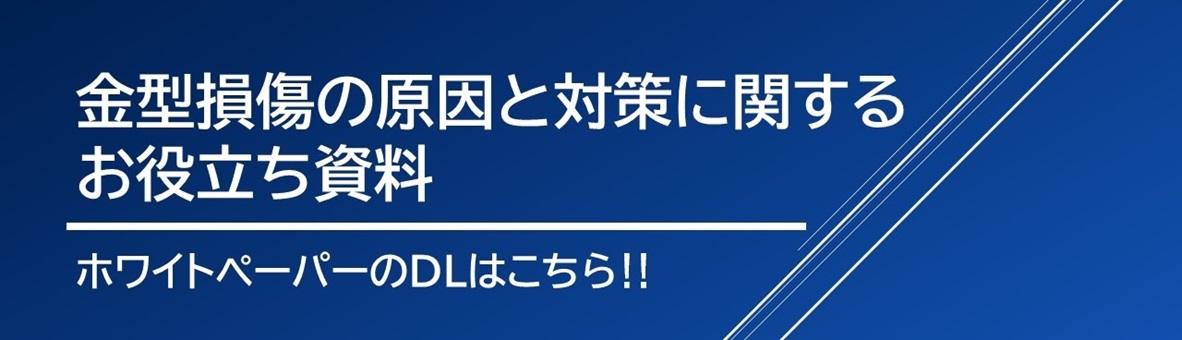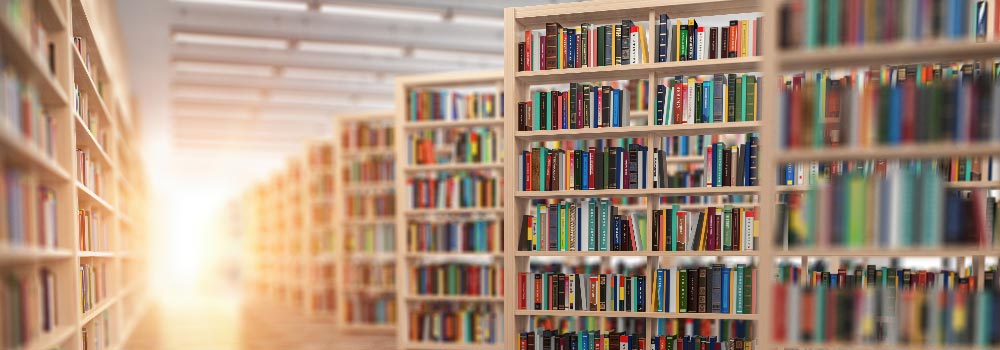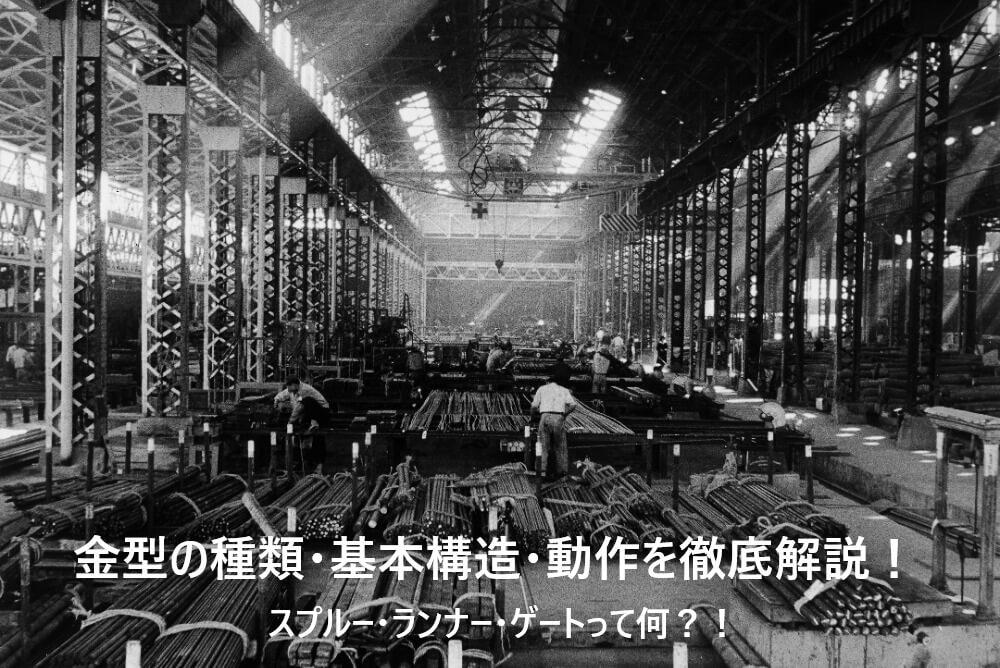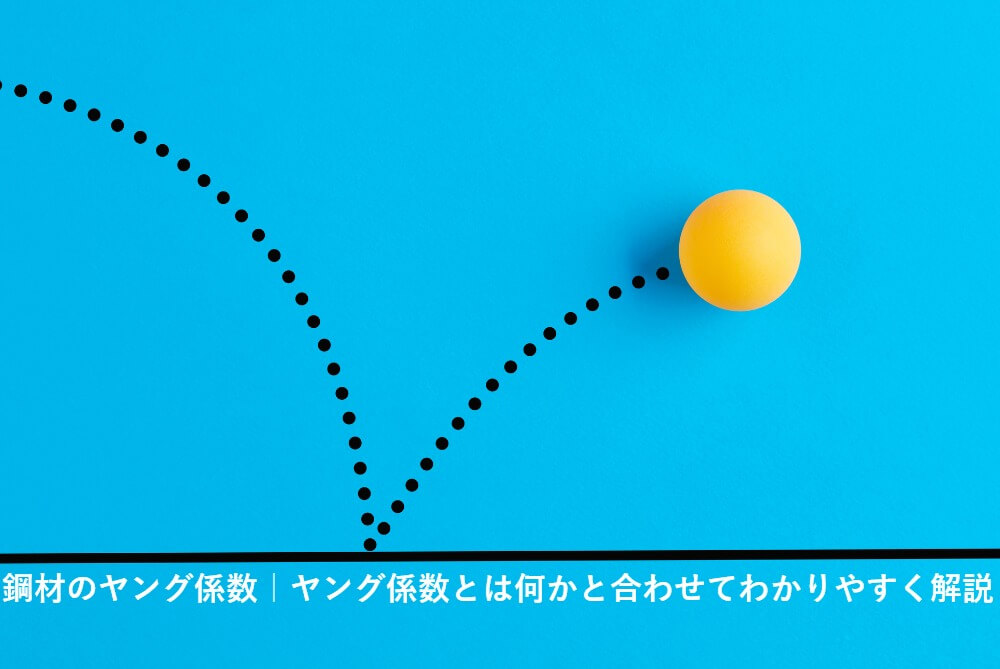鋼材の曲げ加工とは|特徴や種類、注意点をわかりやすく解説
2022年9月15日 2025年6月30日更新

この記事では、自社製品の開発において鋼材の使用を検討している担当者や経営者に向けて、鋼材の曲げ加工について解説します。
鋼材の曲げ加工の概要や特徴とともに、具体的な方法や加工時の注意点についても解説するため、
製品をイメージどおりに仕上げるためにぜひ参考にしてください。
1.鋼材の曲げ加工とは
鋼材(こうざい)とは
鋼材とは、鋼鉄を工業材料として製造したものです。炭素量が0.02~2.1%の金属を鋼鉄とよびます。
鉄は、純度100%の状態で使用するケースはほとんどありません。
炭素量を増やすと強度を高められるため、手を加えたうえで使用するのが一般的です。
「鉄」とよばれているのは、基本的に炭素量を増やしたものです。
鋼材には、工具鋼、特殊用途鋼、機械構造用鋼、圧延鋼材など、さまざまな種類があります。
鋼材を製品にするためには、加工により形状を整える必要があります。鋼材は、ステンレスやアルミよりも加工しやすいうえに安価です。
また、金属には、一定以上の力を加えると形状がもとに戻らなくなる「塑性」という性質があります。
鋼材の曲げ加工は、この性質を利用した加工方法です。
曲げ加工とは
曲げ加工とは、金属の加工方法のひとつです。曲げ加工の方法には複数の種類があります。
加工方法によって、作り出せる形状や特徴はさまざまです。また、金属を曲げるための仕組みにも違いがあります。
複雑な製品を作る場合は、曲げ加工を何度も行ったり、複数の曲げ加工の方法を組み合わせたりします。
製品が複雑な形状になるほどさまざまな要素が必要になるため、高度な加工技術が必要です。
また、作りたい製品にあわせて曲げ加工の方法を使い分ける必要があります。
曲げ加工には注意点もあるため、製品の設計を進めたり加工を依頼したりする際は曲げ加工についての知識があると役立つでしょう。
曲げ加工の基礎知識については以下で解説しますので、ぜひ参考にしてください。
2.鋼材の曲げ加工|方法や温度の特徴
鋼材の曲げ加工の方法としては、冷間曲げ、熱間曲げ、炎加熱による曲げがあります。
冷間曲げは、常温から720度までの範囲で鋼材に圧力をかける方法です。熱間曲げは、800度から900度までの範囲で鋼材を加工します。
炎加熱による曲げは、曲げたい箇所のみを加熱し、その後冷却して鋼材を曲げます。
鋼材は温度によって強度が上がったり脆くなったりするため、加工する際は温度管理の徹底が重要です。
以下では、それぞれの加工方法についてくわしく解説します。
冷間曲げとは
冷間曲げは、常温から720度までの範囲で鋼材を曲げる加工方法です。専用の機械を使用し、曲げたい箇所に圧力をかけます。
具体的には、ベンダー曲げやロール曲げなどの加工方法があります。いずれも、冷間曲げとしてよく利用されている加工方法です。
熱間曲げとは
熱間曲げは、800度から900度までの範囲で鋼材を曲げる加工方法です。
温度を800度から900度までに限定し、鋼材の強度が上がったり脆くなったりする温度を避けて加工します。
熱間曲げでは、冷間曲げよりも小さな圧力で加工できます。より大きく曲げたり大きなひずみを与えたりすることが可能です。
半径を小さくしたい場合や鋭角に曲げたい場合に向いています。また、板厚や板幅が大きい鋼材も加工しやすいです。
炎加熱による曲げとは
炎加熱による曲げは、膨張や収縮する力を利用して鋼材を曲げる加工方法です。
曲げたい箇所を局部的に加熱して加工するため、対象となる鋼材が大きくても高い精度で曲げられます。
熱で膨張させた後、水で冷やして収縮させる仕組みです。炎加熱による曲げの方法としては、線状加熱加工があります。
3.鋼材の曲げ加工|可能なサイズと板厚
鋼材の曲げ加工ができるサイズや板厚は、加工方法や加工する機械によって異なります。
また、鋼材の炭素の含有量によっても、曲げ加工が可能かどうかは変化します。
板厚が厚かったり炭素の含有量が多かったりすると、その分だけ曲げ加工の難易度は上がるのが一般的です。
実際に曲げ加工が可能かどうかは細かい条件によって決まるため、くわしく確認するには加工を依頼する業者への問い合わせが必要です。
4.鋼材の曲げ加工|種類
【冷間曲げ】ベンダー曲げ(型曲げ)
冷間曲げのベンダー曲げ(型曲げ)は、金属を機械に固定して曲げる方法です。
機械にはダイとよばれる金型がついており、パンチによって圧力をかけます。
使用する機械は、プレスブレーキ(ベンダー)やフォールディングマシンなどのプレス機です。
パンチの形状によって、曲げた部分の形状や具合に大きな影響が出ます。
そのため、ベンダー曲げ(型曲げ)にも、突き曲げや迎え巻き上げなどの種類があります。
部品や製品をまとめて大量生産したい場合に向いている加工方法です。
ただし、ロール曲げのような筒状の加工はできません。
スプリングバックを考慮して設計する必要があり、この点については詳細を後述します。
V曲げ
V曲げは、ベンダー曲げのなかで最も一般的な加工方法です。金型に金属を固定し、パンチで圧力をかけてV字に曲げます。
V曲げの加工技術は、ボトミング、コイニング、パーシャルベンディング(エアベンディング・自由曲げ)の3つに大別が可能です。
用途にあわせて使い分ければ、精度の高い曲げ加工を実現できます。
L曲げ
L曲げは、金型に金属を固定してプレスし、L字に曲げる加工方法です。
L字曲げを応用し、曲げ線を2次元または3次元的な曲線にする「フランジ成形」という加工技術も存在します。
曲げ線を内側に湾曲させる加工技術は、伸びフランジ成形です。
一方、曲げ線を外側に湾曲させる加工技術は、縮みフランジ成形とよばれています。
Z曲げ(段曲げ)
Z曲げ(段曲げ)は、金型に金属を固定し、Z字(階段状)に曲げる加工方法です。
専用の金型を使用して1度でZ字に仕上げる方法だけでなく、V曲げを2回行って曲げる方法もあります。
R曲げ
R曲げは、金属に丸みをもたせるように曲げる加工方法です。基本的には、R型の金型に金属を固定して加工します。
ただし、V字の金型を使用し、R曲げを行う場合もあります。
U曲げ(逆押さえ曲げ)
U曲げ(逆押さえ曲げ)は、金型に金属を固定してプレスし、U字に曲げる加工方法です。
パンチと逆押さえによって圧力をかけ、金属をU字に曲げる仕組みです。
P曲げ
P曲げは、金型に金属を固定し、プレスでP字に丸めながら曲げる加工方法です。材料を90度以上に曲げて返します。
O曲げ(円筒曲げ)
O曲げ(円筒曲げ)は、金型に金属を固定してO字に丸めて曲げる加工方法です。複数の工程により金属を曲げ、筒状に仕上げます。
ヘミング曲げ
ヘミング曲げは、金属の縁を曲げる加工方法です。縁を曲げると、製品の安全性が高まるだけでなく、厚みが出て強度も増します。
ほかの加工方法とは異なり、製品の形状そのものを大きく変えるわけではありません。
ただし、安全性、手触り、見栄えをよりよくするためによく用いられています。
【冷間曲げ】ロール曲げ、ロール成形(送り曲げ)
冷間曲げのロール曲げは、3本のローラーを使って金属を曲げる加工方法です。
ロール成形は、ペアになっている複数のロールにコイル状の鋼材を通し、連続的に金属を曲げていきます。
送り曲げは、金型に固定せず、流れ作業によって金属を曲げる加工方法です。
ロール曲げやロール成形を行えば、金属をよりさまざまな形状に曲げられます。筒状の部品にも加工が可能です。ただし、加工できる厚みには限界もあるため、注意しましょう。
【熱間曲げ】
熱間曲げは、鋼をバーナーで加熱して柔らかくし、圧力により曲げる加工方法です。
金属には温めると変形しやすくなる性質があるため、それを利用して曲げ加工を行います。
冷間曲げよりも小さい圧力で金属を曲げられる点が特徴的です。熱間曲げなら、
鋭角の曲げや半径が小さい曲げなども表現できます。
【炎加熱による曲げ】線状加熱加工
炎加熱による曲げの線状加熱加工は、鋼を火であぶって膨張させた後、水で冷却して収縮させて曲げる加工方法です。
右手にアセチレンバーナーを持ち、左手でホースを持って水をかけます。
最初は火であぶっている側とは逆に曲がりますが、水をかけるとあぶった側に曲がってきます。
大きな鋼板を加工する場合も、複雑な曲げや絞りを実現可能です。主に造船業で行われます。
5.鋼材の曲げ加工|加工事例・製品事例
鋼材の曲げ加工を行えば、さまざまな製品を作り出せます。たとえば、金属を加工して一部を曲げれば、ブラケットの製造が可能です。
基盤ボックスや電源装置の部品なども、曲げ加工により自由に作れます。
パソコンのフレームのように細かい形状であっても、複数の加工方法を組みあわせれば高い精度で製造できます。
アイデアや工夫次第では、ほかにも幅広い製品の開発のために鋼材の曲げ加工を利用できるでしょう。
6.鋼材の曲げ加工|注意点
スプリングバックを考慮する必要がある
スプリングバックとは、金型に金属を固定して曲げた後、もとの形状に戻ってしまう現象です。
スプリングバックを考慮しないとイメージどおりの製品を作れない可能性があるため、注意しましょう。
スプリングバックに配慮するには、事前にスプリングバックの戻りを計算しておく必要があります。
スプリングバックが起きる性質を利用して加工する2段曲げや、スプリングバックを防止するストライキングなどを検討しましょう。
製品や部品を設計する際にも注意が必要
鋼材の曲げ加工を行う場合は、設計の際にも気をつけるべきことがあります。
たとえば、曲げ加工とともに穴あけ加工を行うなら、十分な間隔を空けておかないと想定外のひずみが生じる恐れがあります。
展開寸法(展開長)や最小曲げ半径などについても配慮し、イメージどおりの製品を作れるようにしましょう。
加工する際、金属にどのような影響が出るのか理解しておくことが大切です。
7.まとめ
鋼材の曲げ加工にはさまざまな方法があります。最適な方法を選べば、イメージどおりの製品を実現できるでしょう。
そのためには、それぞれの加工方法の特徴を押さえたうえで、企画や設計などを進めることが重要です。
弊社は厳選した原料による清浄度の高い鋼材料の開発力や、伝統的な製鉄技術を用いた製品やサービスを提供しています。
弊社の金型材料(YSSヤスキハガネ®)は、用途に応じて原料の組み合わせや比率を変え、
独自の溶解精錬技術と熱間加工技術を駆使して製造しております。
また、お客様のご要望や製品用途に合わせた最適な材料を提案しております。
金型材料をお探しでしたら、まずは弊社にお気軽にお問い合わせください。
当社の製品に関するご相談やご質問は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
- ※YSS、ヤスキハガネ、YSSヤスキハガネは株式会社プロテリアルの登録商標です。