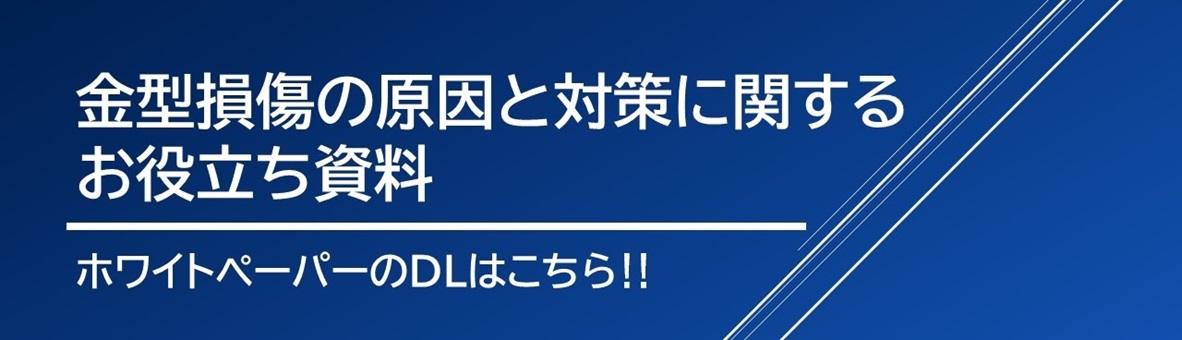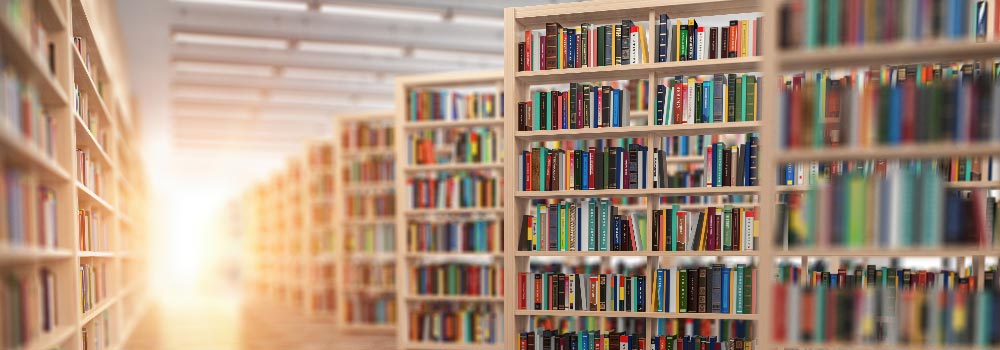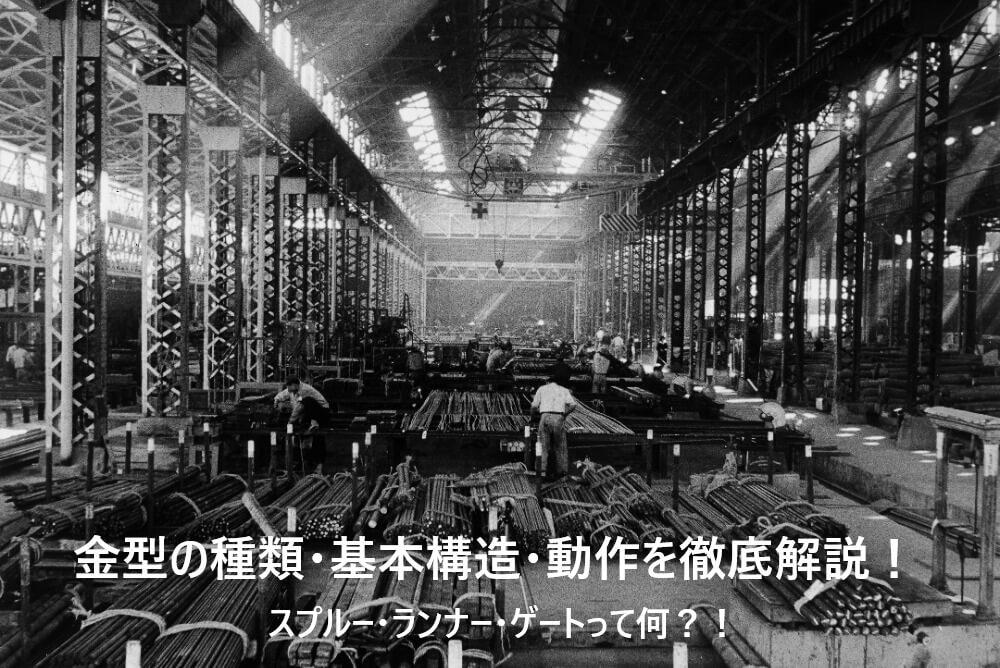合金工具鋼(SKS・SKD・SKT)とは?
種類別の用途や特徴、材料記号、加工方法を解説
2022年9月29日 2025年6月30日更新
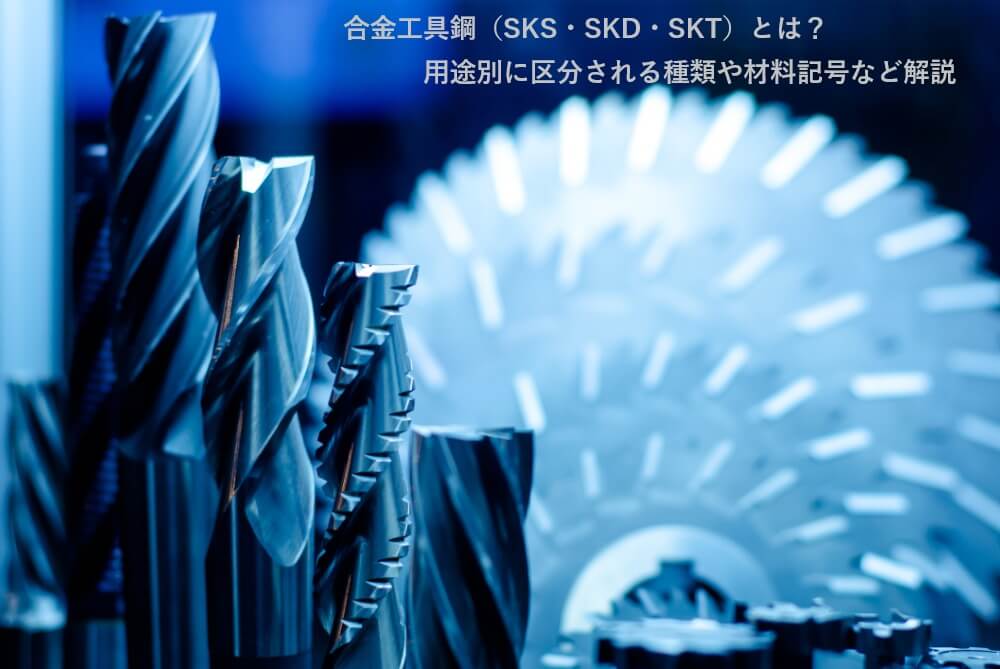
この記事では、合金工具鋼とはどのような鋼材であるかを簡潔に解説し、さらに用途別に区分される種類や材料記号などについても説明します。業務や、用途に応じた材料選びにぜひ参考にしてください。
1.合金工具鋼とは
合金工具鋼とは、工具鋼のうちSKS、SKD、SKTに該当するものです。基準となるものはSK材(炭素工具鋼材)で、ここにW(タングステン)、Cr(クロム)、Mo(モリブデン)、V(バナジウム)などを添加し、耐摩耗性、耐衝撃性、不変形性、耐熱性を高めた鋼材を、合金工具鋼と呼んでいます。
合金工具鋼の使用用途
「工具鋼」という名称のとおり、合金工具鋼の用途は工具の部品です。いずれも非常に硬い金属ですが、そのなかでも金属の配合によって特徴が異なります。種類ごとに適した用途が違うため、主には用途によって合金工具鋼を選択することが一般的です。
合金工具鋼の性質
合金工具鋼は、炭素工具鋼と比べて、焼入性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れる特性があります。また、炭素量や合金元素の種類や含有量によっても、さまざまな性質があります。
2.合金工具鋼、炭素工具鋼や高速度工具鋼との違いを解説
合金工具鋼と名称が似たものに、炭素工具鋼、高速度工具鋼があります。合金工具鋼との違いをそれぞれ解説します。
炭素工具鋼鋼材(SK材)との違い
SK材の「SK」は「Steel Kougu」の略です。C(炭素)の含有量によって、11品種に分類されています。
炭素工具鋼の用途
炭素工具鋼SKは基本的に硬度があり、耐摩耗性にも優れています。ただし高温下では硬度が低下するという特徴があるため、用途は熱の発生が比較的少ない製品に使用されることがほとんどです。
用途としては工具に使われることが多いため「炭素工具鋼」と呼ばれていますが、工具以外に耐摩耗性を求められる部品に使われることも多々あります。
具体的には、ノコギリや錐などの工具、ばねやゼンマイ、農機具から自動車の部品、工場の機械部品など、さまざまです。
高速度工具鋼(SKH材)との違い
高速度工具鋼「SKH」は「Steel Kougu High-speed」の略で、「ハイス鋼」とも呼ばれている鋼の一種です。主に切削工具に使用される鉄鋼材料で、Cr(クロム)やC(炭素)、W(タングステン)、Mo(モリブデン)、V(バナジウム)などの合金元素を含有することによって、非常に高い硬度を誇ります。
高速度工具鋼の用途
合金の含有量によって15種類のSKH材がJIS規格に規定されていますが、その特徴から大きく耐摩耗性に優れるタングステン系と、靭性が良好なモリブデン系の2種類に分けられます。主に切削工具に用いられますが、切削工具だけでなく、熱間加工・冷間加工用途の金型などとしても使われることがあります。
3.合金工具鋼の種類と特徴
合金工具鋼は、JIS規格においては主用途によって4つに区分されています。ここでは合金工具鋼の4つの用途と特徴について、それぞれ解説します。
切削工具用
切削工具用の合金工具鋼は、焼入れ硬さが高いため切削工具に向いたものが分類されており、JISでは8鋼種の規定があります。
切削工具用の合金工具鋼 JIS鋼種:SKS11、SKS2、SKS21、SKS5、SKS51、SKS7、SKS81、SKS8
具体的な用途も名称のとおり切削用で、ドリル、丸ノコ、帯ノコ、やすりなどに適した工具用の金属です。 実際には、SK材に対して、切削工具用合金工具鋼のCr、W、V、Niなどの含有量は多くはなく、 炭素工具鋼とほぼ同じ用途にも使われることがあります。
しかし、SK材に比べて耐摩耗性、耐衝撃性といった部分で優れているため、 より丈夫さが必要とされる切削用の用途に主に使われているのです。
耐衝撃工具用
耐衝撃工具用の合金工具鋼は、衝撃に強いことが特徴です。JISでは4鋼種の規定があります。
耐衝撃工具用の合金工具鋼 JIS鋼種:SKS4、SKS41、SKS43、SKS44
適した用途としては、たがね、ポンチ、スナップなどが挙げられます。これらの用途で大切なのは、硬度よりもむしろ靱性、つまり金属としての粘り強さです。したがって、含有する炭素量を減らし、その分CrやWを多く添加してつくられています。この結果、他の合金工具鋼に比べて硬度は落ちますが、その分衝撃に強い合金となります。
なお、耐衝撃工具用の合金工具鋼の硬さはHRC53~55程度です。他の合金工具鋼の硬さがHRC61以上になることを考えると、靱性の強さが際立ちます。
熱間金型用
熱間金型用の合金工具鋼については、JISにおいて10種類の規定があります。これらの種類については以下のとおりです。
熱間金型用の合金工具鋼 JIS鋼種:SKD4、SKD5、SKD6、SKD61(DAC®)、SKD62、SKD7、SKD8、SKT3、SKT4(DM)、SKT6
これらのうち、SKDは「熱間ダイス鋼」、SKTは「鍛造用型鋼」を示しています。用途に応じて成分の配合が変えられていますが、いずれのケースも熱間、すなわち高温下の作業においても硬度が高く、耐摩耗性に優れ、さらにヒートクラックにも強いのが特徴です。
冷間金型用
冷間金型用の合金工具鋼は、耐摩耗性が大きいのが特徴ですが、それだけではなく焼き入れ後の変形が少ないことも冷間金型用として使われる理由です。JIS規格では、冷間金型用として10鋼種が規定されています。とりわけSKD11、SKS3、SKS93は、「冷間3鋼種」と言われています。
冷間金型用の合金工具鋼 JIS鋼種:SKS3(SGT®)、SKS31、SKS93(YCS®3)、SKS94、SKS95、SKD1、SKD2、SKD10、SKD11(SLD®)、SKD12
冷間金型用の合金工具鋼は、焼入れをおこなってもほとんど膨張がみられない素材で、ゲージ、プレス型などに適しています。これは硬さが高く変形も少ないためですが、その代償として機械加工性が悪く、焼入れ温度も高温になる傾向で、SKD11の場合は1,000度前後の高温環境が必要です。
4.合金工具鋼の材料記号
次に、合金工具鋼の材料記号について解説します。材料記号は、合金工具鋼の用途や素材によって細かく分けられているものです。
JIS規格とISOの対照表
合金工具鋼の規格は、JISのほかにISOでも定められています。ISOは国際規格で、金属素材に対して国境を越えた共通の規格が設けられ、共通の規格番号が与えられており、JIS規格はこれに対応して日本独自の番号を付与しているものです。
ただし、JIS規格にあってもISOに規格がないものもあります。ここでは、JIS規格に規定のある材料記号を具体的に挙げて、ISOと照合しながら紹介します。
切削工具用
切削工具用の合金工具鋼8種類の一覧は以下のとおりです。ISOでの規格はありません。
耐衝撃工具用
耐衝撃工具用の合金工具鋼は4種類です。
冷間金型用
冷間金型用の合金工具鋼10種類のJIS規格です。一部、ISO規格に対応しているものがあります。
熱間金型用
熱間金型用の合金工具鋼は10種類です。ISO規格に対応しているものも多く存在します。
5.合金工具鋼の加工方法
合金工具鋼の加工方法は、主に切削加工と放電加工に分けられます。
切削加工
切削加工とは、工具を用いて金属を削ったり穴を開けたりする加工技術です。一般的には、工作機械が使われます。合金工具鋼では、熱処理前に切削加工で成形し、熱処理後に切削加工や研削加工で仕上げる方法が一般的です。加工する材料や硬さによって、切削速度、送り速度、加工深さ、冷却方法などの、適切な加工条件が異なります。被加工材に適した加工条件を選びましょう。
放電加工
放電加工とは、材料と電極との間で発生した電気エネルギーにより、材料表面を溶かすことで成形する加工方法です。金属を溶かすため、硬度が高い金属も加工ができる特徴があります。ただし、割れや変形などが生じる可能性があるため、注意が必要です。
6.まとめ
合金工具鋼は、工具用に金属中の元素を調整してつくられたもので、いずれも工具によく適した素材となっています。ただし合金工具鋼のなかでも、硬度が低く靱性が高いものや、硬度が高く耐摩耗性に優れたものなど多くの種類があり、用途によって種類を厳選する必要があります。
当社は厳選した原料による清浄度の高い鋼材料の開発力や、伝統的な製鉄技術を用いた製品やサービスを提供しています。当社の金型材料(YSSヤスキハガネ®)は、用途に応じて原料の組み合わせや比率を変え、独自の溶解精錬技術と熱間加工技術を駆使して製造しております。
また、お客様のご要望や製品用途に合わせた最適な材料を提案しております。金型材料をお探しでしたら、まずは当社にお気軽にお問い合わせください。当社の製品に関するご相談やご質問は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
- ※YSS、ヤスキハガネ、YSSヤスキハガネ、DAC、SLD、SGT、YCSは株式会社プロテリアルの登録商標です。