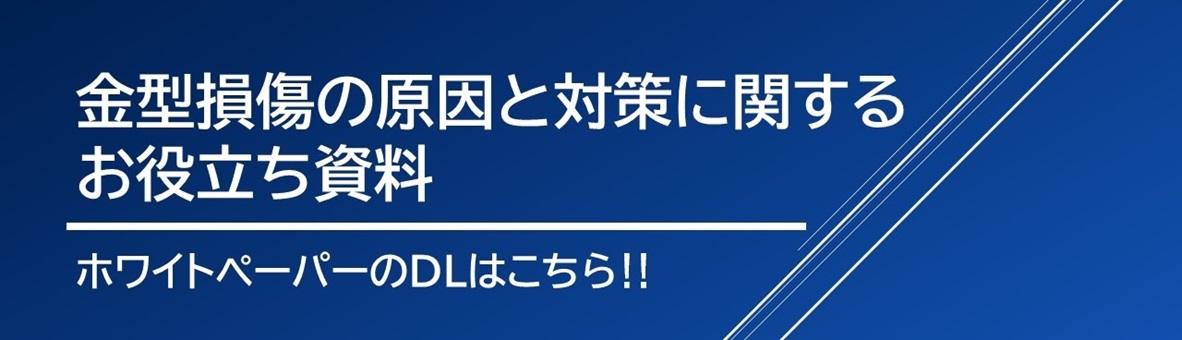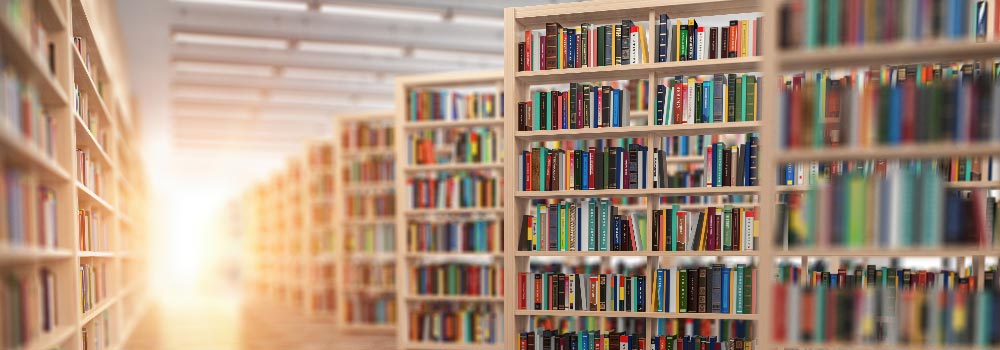鋼材(金型)にはどのような加工方法がある?
加工方法ごとのメリット・デメリットも解説
2022年9月22日 2025年6月30日更新
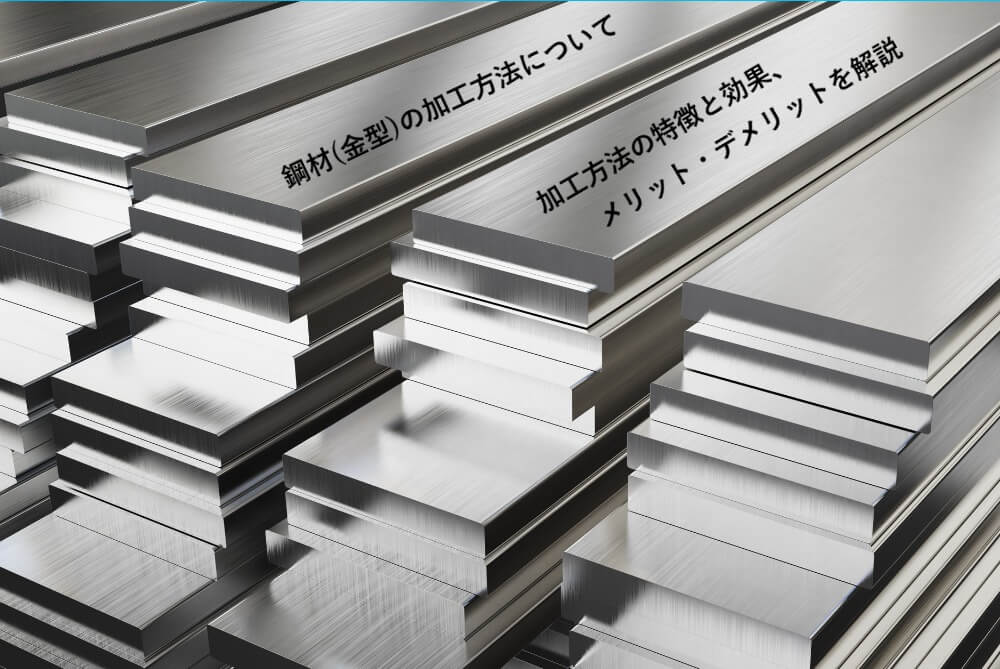
鋼材(金型)は、主に切削加工や研削加工によって作られています。補修のために溶接が行われる場合もあります。つまり、金型製造の基本的な流れは、荒加工、熱処理、仕上げ加工、溶接です。 この記事では、金型製造に携わっている製造業の担当者に向けて、鋼材の加工方法について解説します。鋼材の加工方法について理解を深めるために、ぜひ役立ててください。
1.鋼の種類
加工方法について解説する前に、ここでは鋼の種類を解説します。
工具鋼
さまざまな工具や刃物に用いられる工具鋼は、含まれている成分により分類されています。
炭素工具鋼
炭素工具鋼は、0.02~2.14%程度の炭素を含む鋼材です。炭素のほかにも、ケイ素、マンガン、不純物リン、硫黄、銅などを含んでいます。炭素の量が多くなるほど硬度が高くなります。焼戻しを行うと、さらに硬度を高められます。
ただし、硬度が高くなるとその分だけもろくなるため、注意も必要です。炭素工具鋼は金型だけでなく、ほかにも幅広い製品に使用されています。
合金工具鋼
合金工具鋼は、炭素工具鋼にCr(クロム)、W(タングステン)、Mo(モリブデン)、V(バナジウム)などを加えた鋼材です。これらの添加により、摩擦、衝撃、熱などに強くなります。合金工具鋼は切削用、耐衝撃用、冷間金型用、熱間金型用の4つに分類可能です。なお、当社の製品は合金工具鋼が主となっています。
機械構造用鋼
建設機械や産業機械、自動車などの主要な部品の材料として使われているのが、機械構造用鋼です。一般的な機械構造用の機械構造用炭素鋼、強度や靭性、疲労耐性などを高めた機械構造用合金鋼があります。
特殊用途鋼
特殊用途鋼とは、構造用鋼や工具鋼以外の鋼材で、用途が限定されたものです。ばね鋼、クロム軸受鋼、快削鋼、ステンレス鋼などがあります。炭素以外の金属元素を添加することで、性能を高めています。
強度や耐熱性を高めるニッケル、サビにくくなるクロムやチタン、硬度を高めて変形しにくくするマンガンなどが挙げられます。
2.鋼材の形状による分類
鋼材には、形状による名称もあります。ここでは、各形状の名称と特徴について解説します。
圧延鋼材
鋼材の加工において「圧延」とは、2つのローラーの間に金属を通して押しつぶす方法を指します。圧延鋼材は、用途によって一般構造用圧延鋼材、溶接構造用圧延鋼材、建築構造用圧延鋼材などに分類されます。飲料缶、車体や船体、建材、橋梁や建築構造物の材料など、幅広い分野に普及しています。
鋼板
鋼板は、板状に加工した鋼材です。厚さが3ミリ未満のものは薄鋼板、3ミリ以上6ミリ未満は中鋼板、6ミリ以上を厚鋼板と呼びます。自動車や各種車両、電気機器、防音壁、ガードレールなど、幅広く使われています。
鋼管
筒状に加工された鋼材を、鋼管と呼びます。加工方法により「継目(つぎめ)無鋼管」と「溶接鋼管」に分類されます。鋼管が使われている例としては、建物の骨組み、ガス管や水道管などのパイプラインなどが挙げられます。
形鋼
形鋼(かたこう)とは、断面がさまざまな形状になっている鋼材です。断面の形状により、H形鋼、I形鋼、山形鋼、溝形鋼といった名称がつけられています。建物の柱や窓のサッシ、手すり、高速道路や橋梁などの構造材など、幅広く使われています。
棒鋼
棒鋼とは、棒状に成形された鋼材です。断面の形状により、丸鋼・四角鋼、六角鋼、八角鋼などと呼ばれています。棒鋼は、建設物の鉄筋、機械の構造材、ボルトやナットなどに使われています。
3.鋼材(金型製作)に用いられる加工方法
ここでは、鋼材(金型製作)に用いられるそれぞれの加工方法について、くわしく解説します。
①切削加工
切削加工とは、工具を使用して鋼材を削ったり穴を開けたりする加工方法です。ただし、切削加工について厳密な定義があるわけではありません。基本的に切削加工はさまざまな形状やサイズに対応でき、幅広い加工が可能です。
切削加工は鋼材の加工において、一般的によく用いられています。切削加工を行う際は、旋盤、ボール盤、フライス盤などを使用します。製造したい個数が少量でも対応可能です。
メリット・デメリット
切削加工なら幅広い加工が可能なため、自由度の高い製造を実現できます。高い精度で加工できる点も大きなメリットです。また、対応できる材質の種類も多いです。少量生産に向いている反面、大量生産にはあまり向いていません。また、加工のために使用する刃物が摩耗していると、仕上がりの品質が下がります。
②研削加工
研削加工は、研削用の砥石を高速回転させて鋼材を加工する方法です。砥石で鋼材の表面を少しずつ削る加工方法であり、切削加工のように鋼材に穴を空けることはできません。切削加工を行った後に仕上げとして研削加工を行う場合が多いです。
高い精度で仕上げができるため、品質にこだわりたい場合にも向いています。具体的には、0.1ミクロン単位での調整が可能です。
メリット・デメリット
研削加工を施すと、製品の表面がより滑らかになります。そのため、精度の高い製品を製造できます。硬い素材も問題なく加工でき、さまざまな製品の仕上げが可能です。ただし、研削加工では製品の表面を少しずつ削るため、加工に時間がかかります。砥石のメンテナンスも定期的に行わなければなりません。
③磨き加工
磨き加工は、製品の表面を磨く仕上げの加工方法です。磨き加工は研磨加工ともよばれており、さまざまな種類があります。具体的には、ラッピング研磨、バフ研磨、砥石研磨、バレル研磨、電解研磨などがあります。
磨き加工をすると表面の凹凸がなくなるため、製品の美観を向上させることが可能です。汚れやサビも防止できます。高い強度や精度が求められている製品には、最後に磨き加工が行われる場合が多いです。
メリット・デメリット
磨き加工を行うと、製品の断面の凹凸がなくなって見た目がよくなります。また、塗装しやすくなるというメリットもあります。ただし、磨き加工の種類によっては、コストが高くなる場合もあるため、注意が必要です。具体的には、ラッピング研磨や電解研磨を行うと、特にコストがかかります。
④溶接加工
溶接加工は、鋼材と鋼材を接合するための加工方法です。熱を与えたり圧力を加えたりし、鋼材同士をつなぎあわせます。溶接するものは「溶加材」、溶加材に溶接する鋼材部品は「被溶接材」とよばれています。
溶接は、具体的には融接、圧接、ろう接の3種類に大別可能です。融接は、さらにアーク溶接やガス溶接などの種類があります。圧接としては、抵抗溶接が代表的です。ろう接としては、ろう付けやはんだ付けがあります。
メリット・デメリット
溶接加工は、比較的簡単に施せる加工方法です。加工にかかる時間も短いというメリットがあります。また、気密性や水密性も保持できます。ただし、寸法の精度を維持するのは難しいです。ボルトやネジによる接合とは異なり、鋼材同士を一度接合すると簡単には解体できません。その点を理解したうえで溶接加工を行いましょう。
⑤放電加工
放電加工とは、放電によって発生する火花の熱を活用する加工方法です。鋼材と加工機の間に放電し、熱を発生させます。放電加工は、EDM(Electrical Discharge Machining)とよばれる場合もあります。放電加工は、硬度が非常に高い材質でも加工が可能です。切削加工では加工できない鋼材も加工でき、削ったり穴を空けたりすることもできます。
メリット・デメリット
放電加工は製品を加工液に漬けた状態で加工するため、熱による変異が生じにくいです。
バリも出にくいため、硬度が高い材質を高精度で加工できます。ただし、放電加工では少しずつ加工していくため、時間がかかります。よって、大量生産には向いていません。
⑥ワイヤーカット加工
ワイヤーカット加工は、真鍮でできている細いワイヤーに電流を流し、ワイヤーをのこぎりのように使って鋼材を切断する加工方法です。導電性のある鋼材なら何でも加工できます。放電の際に発生する熱で鋼材を切断する仕組みです。6,000~7,000℃の熱が発生しますが、鋼材には触れずに切断します。
加工液に漬けて加工する点も大きな特徴です。加工槽に冷却装置がついており、高温の熱が発生しても鋼材の変形を防げるようになっています。
メリット・デメリット
ワイヤーカット加工なら、硬い鋼材や厚みのある鋼材も問題なく加工できます。直線と曲線のいずれも表現できるため、加工の精度も高いです。ただし、ワイヤーを垂直に張って糸のこぎりのように使う必要があり、水平加工や底のある加工には向いていません。加工のスピードが速くないため、大量生産にも不向きです。
4.鋼材の加工方法の選び方
鋼材を加工するときは、鋼材の種類と特徴を押さえたうえで最適な方法を選択しましょう。コストや工数なども重要ですが、加工方法のメリットやデメリットなども正しく理解したうえで加工方法を選ぶことが大切です。適切な加工方法を選択すれば、より精度の高い製品を製造しやすくなります。
5.まとめ
鋼材の加工方法はさまざまです。それぞれ特徴やメリット・デメリットに違いがあるため、製品にあわせて選ぶ必要があります。最適な加工方法を選択し、イメージや目的にあう加工を実現しましょう。
当社は厳選した原料による清浄度の高い鋼材料の開発力や、伝統的な製鉄技術を用いた製品やサービスを提供しています。当社の金型材料(YSSヤスキハガネ®)は、用途に応じて原料の組み合わせや比率を変え、独自の溶解精錬技術と熱間加工技術を駆使して製造しております。
また、お客様のご要望や製品用途に合わせた最適な材料を提案しております。金型材料をお探しでしたら、まずは当社にお気軽にお問い合わせください。
当社の製品に関するご相談やご質問は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
- ※YSS、ヤスキハガネ、YSSヤスキハガネは株式会社プロテリアルの登録商標です。