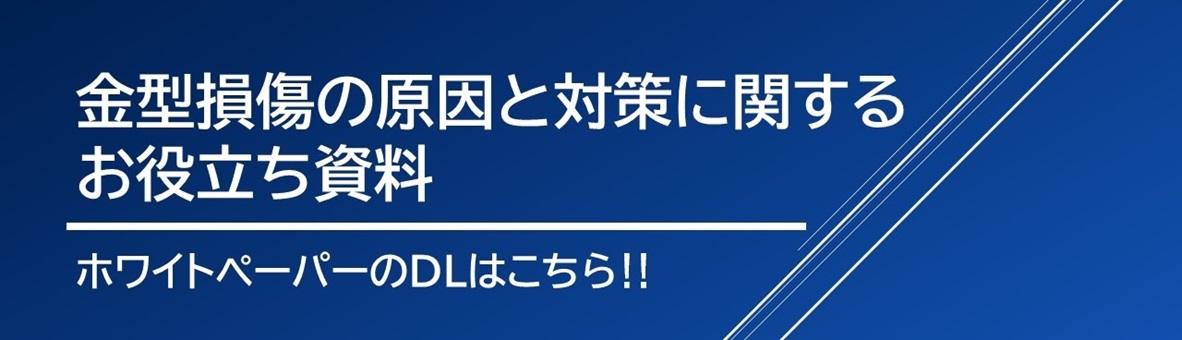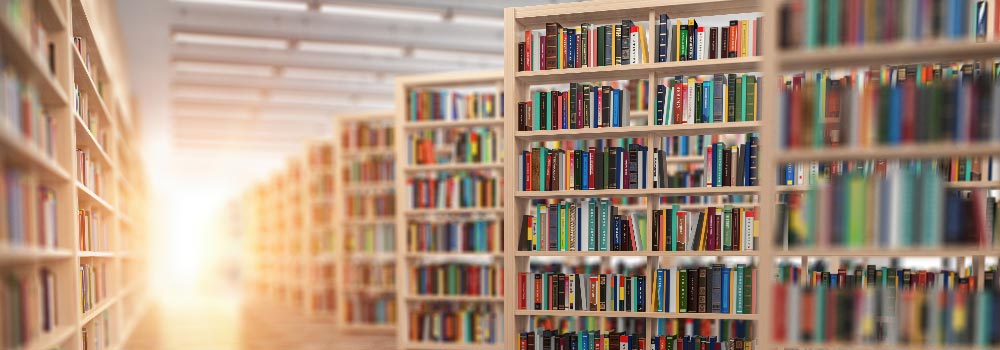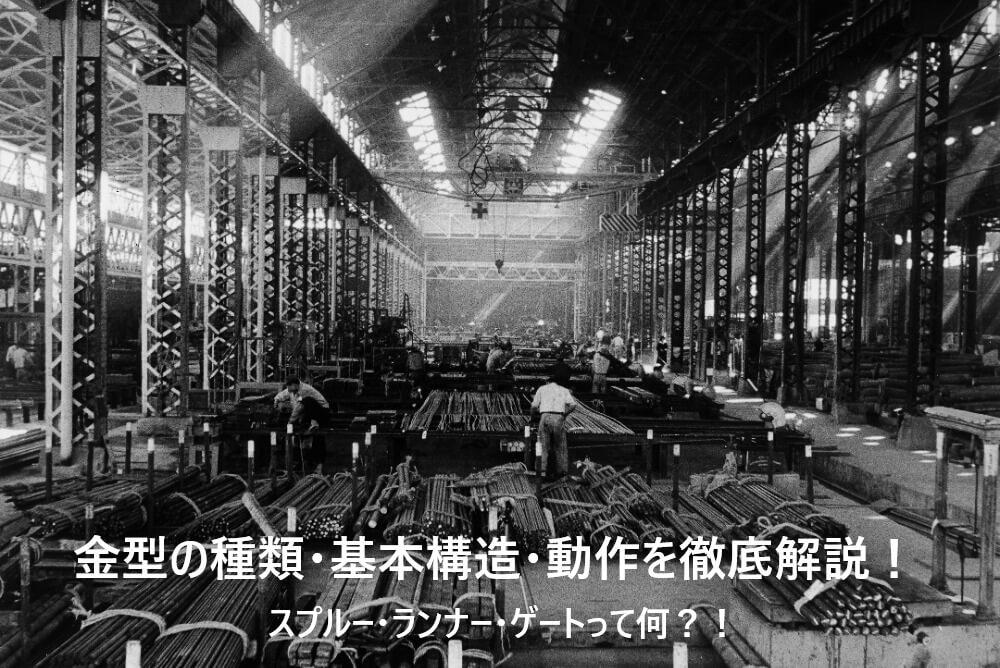鋳造と鍛造の違いとは
加工過程やメリット・注意点や製品例でみる違いなど特徴を解説
2022年8月4日
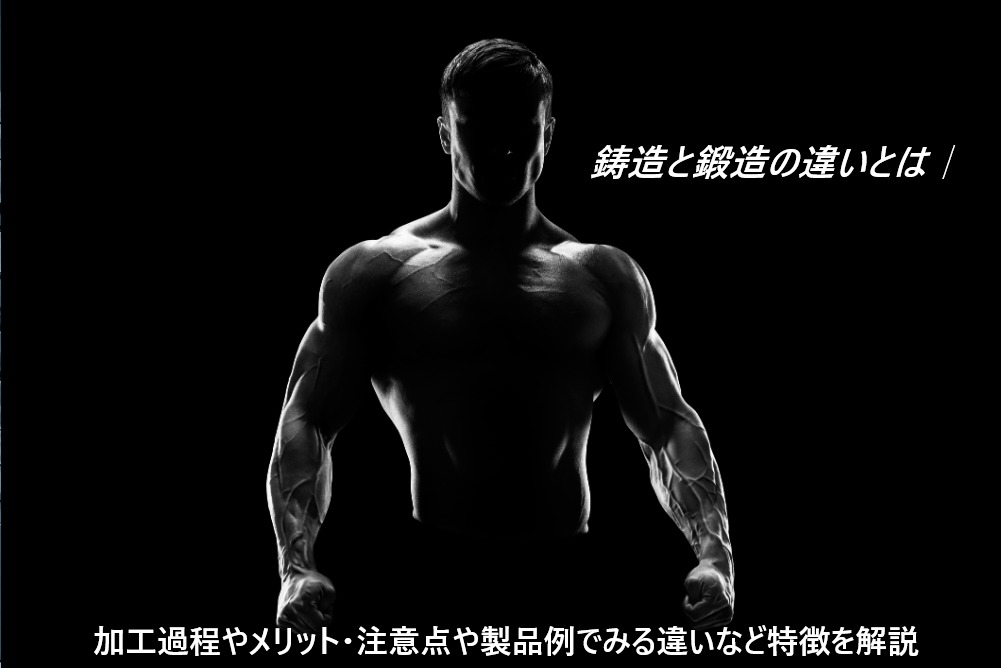
自社製品の加工をする際に、鋳造がよいか鍛造がよいのか悩んでいるという人もいるでしょう。
この記事では、鋳造と鍛造どちらがよいか悩んでいる開発担当者や経営者に向けて、鋳造加工と鍛造加工の違いを解説します。
それぞれのメリットや注意点、製品ごとの違いや使用される材料の違いについても解説するため、加工方法を選ぶ際の参考にしてください。
1.鋳造(ちゅうぞう)と鍛造(たんぞう)の違いとは
鋳造と鍛造は、どちらも金属を成型する加工法です。両者の違いは、溶かして固めるか、叩くもしくは型で圧縮して成型するかにあります。
どちらの加工法でも、同じ見た目の部品は作れます。
しかし、加工法によって強度やコストなどに違いが出るため、適した方法を選びましょう。
それぞれの違いや特徴について、以下で詳しく解説します。
2.鋳造(ちゅうぞう)の特徴
鋳造の加工法
鋳造とは、金属を溶かし固める加工法です。溶かして液体にした金属を、型に流し込んで成型します。
一度金属を液体にするという性質上、形状の自由度が高いことが鋳造の特徴です。
そのため、複雑な形状であっても作成しやすく、比較的安価に作成できる加工法です。
鋳造ではまず、電気炉などで銅や鉄、アルミ合金、真鍮などの金属に熱を加えて溶かし、液状にします。
液状にした金属を取り出すことを出湯と呼んでいます。次に、液体になった金属を任意の型に流し込みますが、この作業が注湯です。
型に流し込んだ金属を冷やし固め、型から取り出して完成です。
鋳造のメリット
鋳造は型の自由度が高く、複雑な形状のものでも比較的安価に加工できます。
また、全体的なコストも鍛造と比べると低めに抑えられるため、コストダウンにつながる点はメリットでしょう。
鋳造の場合、型に金属を流し込むことで同じ形状のものが作成でき、冷却すればすぐに固まるため、短時間で大量生産可能です。
鋳造の場合、型の作成にコストがかかります。しかし、鍛造と比較した場合、木型や発泡型の砂型鋳造なら安く済むため、
多くの品種を少量ずつ生産する場合には、鋳造のほうが向いています。
鋳造の注意点(デメリット)
鋳造の場合、強度が下がってしまうケースがあります。
そのため、製品によっては肉厚にするなどの対策が必要で、鍛造に比べると重くなってしまいます。
強度を下げる要因としては、内部の気泡が挙げられます。液体にして流し込む際に、内部に気泡ができて強度を下げる可能性があるようです。
また、厚みが異なる部分を冷却した際に、応力と呼ばれる物体の内部に生じる力が残り、内側から力がかかってしまうケースもあります。
仕上げ段階で応力を除去することも可能ですが、コストは高くなります。
応力の有無
注意点の中で解説したとおり、鋳造の場合には内部応力が残る場合があります。
内部から力がかかり強度を下げる可能性があるため、注意が必要です。
3.鍛造(たんぞう)の特徴
鍛造の加工法
鍛造とは、金属をハンマーなどで叩いたり、型で圧縮したりして成型する加工法です。鍛造は強度に優れています。
鉄は叩くことで強くなりますが、これは古くから知られている性質です。
鍛造は、ハンマーで何度も叩いて製品の形に近づけていく方法と、金型で圧縮して製品の形に成型する方法に分けられます。
また、叩く方法には、自由鍛造・型鍛造・閉塞鍛造・密閉鍛造があります。
鍛造では、金属を金型に設置し打撃や圧縮によって力を加えていきます。何度も力を加えて加工し、金型から取り出して完了です。
鍛造は「熱間鍛造」・「温間鍛造」・「冷間鍛造」の3種類に大きく分けられます。それぞれの方法について、以下で詳しく解説します。
熱間鍛造・温間鍛造・冷間鍛造の特徴
それぞれの方法は、加工時の温度などの違いによって分類されます。
「熱間鍛造」とは金属を約1,000~1,200℃に熱して加工する方法です。やわらかい状態で加工できるため、加工しやすく自由自在に製品を作れます。
「温間鍛造」とは、金属を約300~850℃に熱して加工する方法です。スケールがつきにくく、後処理の必要がありません。
「冷間鍛造」とは、常温で加工する方法です。金属表面がきれいに仕上がり、精度の高い製品が作れます。
また、鍛造と鋳造を合わせた「溶湯鍛造」という加工方法もあります。
鍛造のメリット
叩いたり圧縮したりする過程で、金属内部の結晶が整い、強度が高まることは鍛造のメリットです。
叩く過程で気泡などの内部欠落を圧着させられるため、粘り強さが出て鋳造よりも強度が高くなります。
また、鍛造は反復曲げ力に強く、内部応力が残りません。金型を活用することにより、大量生産も可能です。
前述したように、型のコストにおいては少量多品種生産の場合鋳造が有利です。
しかし、型を使わない自由鍛造なら、少量多品種生産にも向いています。
人の手で鍛造を行う場合は、サイズや重量など高い精度で製造できるため、重量や強度などの規格が決まっている製品にもよいでしょう。
金属の削り出しなどより材料も少なくて済むため、材料費の節約にもつながります。
鍛造の注意点(デメリット)
鍛造は、鋳造よりもコストが高めになりがちです。また、何度も繰り返して叩いたり圧縮したりするため、加工には時間がかかります。
そのため、一般的には大量生産には不向きな加工法だといえるでしょう。ただし、同じ型を使えば大量生産も可能です。
鍛造の場合、逆勾配形状の加工は不向きです。
鍛造で逆勾配形状の製品を製造したい場合には、勾配がなだらかになるように肉付けし、後から余計な部分を削り取る必要があります。
応力の有無
鋳造のメリットでも解説したように、鍛造では応力は残りません。内部から力がかからないため、強度が低くなることはありません。
4.熱間(ねつかん)加工と冷間(れいかん)加工とは
熱間加工と冷間加工は、優れた金属製品を製造・加工するために使われている冶金方法のことです。
熱間加工とは、900℃~1,200℃で加工する方法です。
金属の再結晶温度以上の温度で行われる加工で、変形に使う力が少ない、加工しやすいなどの特徴があります。
一方、冷間加工とは720℃以下で加工する方法です。
金属の再結晶温度よりも低い温度で行われる加工で、精度の高い加工が可能、材料が硬くなるという特徴があります。
5.鋳造品と鍛造品、製品例から見る違い
鋳造と鍛造は、どのような製品に用いられるのでしょうか。
鋳造の場合、強度に関しては鍛造に劣りますが、複雑な形状の製品を作りやすいというメリットがあります。
そのため、自動車用部品や大量生産のジュエリーなどに向いているでしょう。
一方、鍛造は強度が特に強く、熱が加わっても変形しにくい点がメリットです。
強度が必要な自動車のギアや高温になりやすいエンジン回りの部品、航空機のフレームなどに向いています。
製品の中には、どちらの方法でも作られているものがあるため、以下で詳しく解説します。
≪ゴルフクラブ≫
鋳造ゴルフクラブ
鋳造ゴルフクラブは、初心者向けとしてよく使われます。
鋳造の場合には、複数の素材を組み合わせることができ、ヘッドの形も複雑なものにしやすいです。
たとえば、ステンレスを素材にした鋳造アイアンの場合、金属が硬いため初心者でも飛距離が出しやすくなっています。
扱いやすくミスにも強いため、初心者やアベレージを出したい人に向いています。
鍛造ゴルフクラブ
鍛造ゴルフクラブは、中級者・上級者向けとしてよく使われます。
特に、軟鉄鍛造アイアンの場合は打感がやわらかくて、ライ角が変えやすいという特徴があります。
ライ角とは、地面とシャフトの中心線の角度のことで、中級者や上級者が意識するポイントです。
コストが高くなるという点でも、初心者よりは中・上級者向けだといえるでしょう。
≪アルミホイール≫
鋳造ホイール
鍛造ホイールは、コストが低く抑えられるため価格も安価という特徴があります。
また、複雑な形も作れるため、ホイールのデザインも豊富で、自分の好みや車に合ったホイールを探しやすいでしょう。
ただし、強度に関しては鍛造ホイールよりも劣ります。強度を出すために厚みを増すと、重量が重くなってしまいます。
鍛造ホイール
鍛造ホイールは、軽量かつ高強度です。叩いて金属の密度を上げるため、薄いのに強度の高いホイールを作れます。
軽いため車の性能を引き出しやすい、燃費がよくなるなどのメリットも考えられます。大型の車にもよいでしょう。
ただし、鍛造ホイールはコストが高くなりがちです。そのため、価格も鋳造ホイールよりは高めです。
≪リング(婚約指輪・結婚指輪など)≫
鋳造リング
鋳造リングは、金型に金属を流し込んで製造できるため、大量生産が可能です。
また、複雑な形状にもできるため、かわいいデザインや繊細なデザインなども再現できます。
コストも安く済むため、安価で手に入れやすいリングです。
ただし、鍛造リングよりも耐久性は劣ります。スポーツや家事、力仕事などで歪んでしまうケースもあります。
鍛造リング
鍛造リングは、強度が高く変形しにくい点がメリットです。そのため、結婚指輪などのように毎日つけるようなリングに向いています。
ただし、鍛造リングの場合には繊細なデザインの再現は難しく、シンプルなデザインになってしまいます。
また、手作業で作られる場合が多いため、注文から手元にくるまでに時間がかかるケースが多いようです。
6.加工法を選ぶためには目的や用途を理解することが重要
上述したように、鋳造・鍛造製品の場合には、鍛造品のほうが強度に優れています。
しかし、強度の高さと、精度の高さは必ずしもイコールではありません。
そのため、どのような製品を作るのか、目的や用途などを理解して加工法を選ぶことが重要です。
基本的に、面が少なければ少ないほど鍛造向きの製品だといえます。また、安定した強度が必要な場合にも、鍛造が向いているでしょう。
しかし、鍛造は複雑な形状は作りにくくなっています。
複雑な形や繊細なデザインのものを鍛造で製造しようと思うと、コストはかさんでしまいます。
金属製品の製造を行う際には、消費者の使用環境を考慮し、適切な加工方法を選びましょう。
加工方法ごとのメリットを活かすには、製品の目的や用途への理解を深めることが重要です。
7.鋳造・鍛造によく用いられる材料
鋳造に使われる材料
鋳造にはどのような材料が使われやすいのでしょうか。鋳造に使われる材料としては、以下のようなものが挙げられます。
- 銅
- アルミニウム合金
- マグネシウム合金
- 鋳鉄
- 亜鉛合金
- 銅合金
- ニッケル合金
- チタン合金
鍛造に使われる材料
鍛造に使われる材料として主に挙げられるのが、鉄鋼です。
しかし、鉄鋼以外にも使われている材料はあります。鉄鋼以外の材料は以下のとおりです。
- アルミニウム合金
- ステンレス銅
- 機械構造用合金鋼
- チタン合金
アルミニウム合金やチタン合金が使用されるケースも、近年では増加傾向にあります。
8.まとめ
鋳造と鍛造には、それぞれメリット・デメリットがあります。鍛造のほうが強度は高くなりますが、複雑・繊細な形状には不向きです。
製品の目的や用途などを理解したうえ、自社製品に見合った加工法を選びましょう。
当社には、原料を厳選し清浄度の高い鋼をつくり上げる材料開発力と、伝統の製鋼技術を有しており、
各種グレードの材用を取り揃え、広範囲のニーズにお応え致します。金属素材をお探しならぜひお問い合わせください。
当社の製品に関するご相談やご質問は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。