ABOUT GROWTH

多様な個を
変革と成長の推進力にする
プロテリアルグループは、
ダイバーシティ&インクルージョンを
徹底追求することを
重要な経営戦略として位置づけ、
さまざまな施策に取り組んでいます。
プロテリアル
ダイバーシティ・マネジメント基本方針
-
1.
性別・国籍・文化などの違いを個性として尊重し、併せて女性の活躍促進、グローバル人材の活用を含む多様性を確保することで、イノベーションの推進を図り、リスク・変化への対応の柔軟性・スピードを高めます。
-
2.
コミュニケーションを活発に行い、価値観を共有することで、個人の成長を図り、組織としての実行力を高め、持続的成長の基盤を強化します。
-
3.
ダイバーシティを成長のエンジンとし、グローバルに勝てる事業体に「変革」し、新たな目標に「挑戦」することで、世界トップクラスの高機能材料会社の実現をめざします。
PICK UP.01
女性活躍推進
当社は2015年に行った女性総合職へのヒアリングを契機に、事業所を超えて社内の女性が交流し、多様なキャリアの紹介や課題について話し合う女性フォーラムの開催や、社外研修への派遣、積極的な採用や登用など、女性の活躍を推進する取り組みを実施しています。またパートナーとの家事や育児分担を見直す従業員にパパエプロンを贈呈し、男性に対して家事育児を促すほか、女性の健康セミナーの開催など、女性特有の疾病に対する啓発活動にも取り組んでいます。

TOPICプロテリアル女性フォーラム
当社では「女性フォーラム」という女性総合職のネットワーキングイベントを毎年実施しています。プロテリアルの各事業所にいる女性総合職を集め、女性のキャリアやモチベーション、ワークライフバランス、男性との関わりなどさまざまなテーマでディスカッションを行っております。

TOPICえるぼし認定
「えるぼし」認定は女性活躍推進に関する行動計画の策定・届出を行い、取り組み状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定するもので、基準を満たした評価項目の数に応じて3段階で評価されます。プロテリアルは評価項目のすべてで基準を満たし、2020年5月に3段階目の認定を取得しています。

PICK UP.02
多様な働き方の支援
多様な人材が異なる価値観や考え方を共有し、生産性の高い仕事のやり方や働き方を志向し、仕事の充実感と自らの成長を実感できる環境づくりが不可欠であると考え、ICT施策の推進による業務効率向上やタイムフリー・ロケーションフリー勤務の促進・定着化など、一人ひとりが働きがいや働きやすさを「実感」できるよう、地道な活動を継続してきました。2022年度の間接員年間総実労働時間は2,056時間、年次有給休暇取得率は74%となり2016年度の総実労働時間2,245時間、年次有給休暇取得率48%から大幅に改善されており、生産性の高い「働き方」が浸透してきています。

PICK UP.03
健康経営の推進
健康経営宣言
当社は企業理念に基づき、会社の永続的発展と当社に集う一人ひとりの従業員の幸福のため安全衛生を経営の重要な根幹として位置付け、すべての事業活動において『安全と健康はすべてに優先する』を行動原則とし、心身ともに健全で活力ある人材を育むとともに安全で快適な働きがいのある職場の創出に向けた活動を積極的に推進していきます。
自分と仲間の安全を守り、一人ひとりが自らの健康増進に主体的に関わっていくことができるよう、より一層取り組んでいくことを改めてここに宣言致します。
2023年1月4日
株式会社プロテリアル
TOPIC健康経営優良法人に認定
健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。プロテリアルは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として、健康経営優良法人2025に認定されました。

-
健康増進活動の主な取り組み
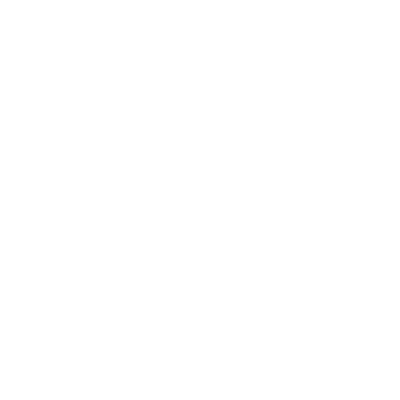

-
-
当社社員の生活習慣について分析したところ、重点的に実施すべき課題として、喫煙率の高さがありました。健康保健組合と連携し、禁煙プログラムの参加勧奨や禁煙セミナーの実施などの活動を通し喫煙率は徐々に低下してきています。2024年度までに喫煙率が30%以下となるよう、2022年度からは全社禁煙推進ロードマップを示し、「スワンデー」の実施などの啓発活動に取り組んでいます。
-
主要事業所においてウォーキングイベントの実施や、健康保険組合と連携した特定保健指導の参加勧奨等、健康増進のための生活習慣の改善につながる活動を積極的に実施しています。
メンタルヘルスに関しては、ストレスチェック制度を毎年実施し、 本人の気づきを促進するとともに、各事業所別にストレスチェック報告会を実施し、集団分析結果に基づいた職場環境の改善を図っています。
-
PICK UP.04
社員を支援する制度
-
出産・育児に関する制度
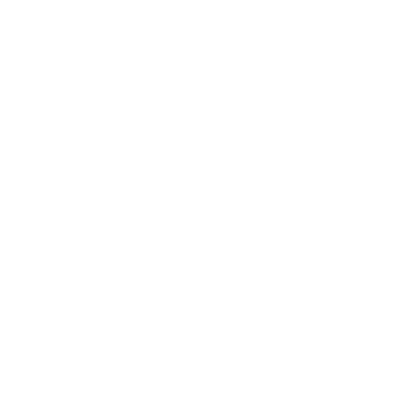

-
-
育児短縮勤務
子が小学校卒業までの間、育児勤務として短時間勤務を行うことができます。短縮時間は15分単位で1日につき最高3時間、男性は出産日又は出産予定日から、 女性は産後休暇終了日の翌日から小学校卒業当日までの期間利用できます。
※連続して短縮できる時間は最高2時間まで -
育児休暇
育児に専念するために休業を申し出たとき、子が小学校1年修了時までのうち、3年を限度に本人の申出た期間とし、半日単位で請求することができます。
-
配偶者出産休暇
配偶者の出産の際の病院の入院・退院、出産の付き添い等を行う場合、出産1回につき5日とし、半日単位に分割して取得することができます。
-
出生時育児休暇
配偶者または同性パートナーが出産予定の方で、出産休暇を取得していないときに取得可能です。予定日または出生日から8週以内(56日以内)で最大4週(28日)の取得が可能です。
※上記期間・日数内であれば2分割まで可能
-
-
多様な家族のかたちを支える制度
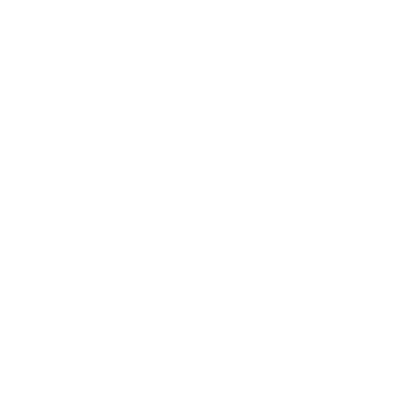

-
-
家族看護休暇
本人、配偶者又は同性パートナーの父母、配偶者、同性パートナー、子を看護するとき1年につき5日とし、連続、1日、半日又は時間単位に分割して請求することができます。
-
家族支援休暇
小学校就学前の子(実子または養子)の看護、要介護状態にある以下の親族の介護本人、配偶者又は同性パートナーの父母、配偶者、同性パートナー、子、祖父母、兄弟姉妹、孫の介護、不妊治療を含めた妊娠・出産をめざす活動のいずれかの目的に必要な場合、1年につき5日とし、半日単位で請求することができます。
-
介護休暇
要介護状態にある家族を介護するために休業を申出たとき、原則として93日以内で本人が申し出た期間とし、半日単位で請求することができ、必要な場合は1年まで延長することができます。
-
年次介護休暇
要介護状態にある本人又は配偶者の父母、配偶者、子、同居しかつ扶養している祖父母、 弟姉妹および孫を介護するとき「1年につき介護対象人数に5日を乗じた日数」の休暇を取得することができます。
-
-
個々に最適な働き方を実現する制度
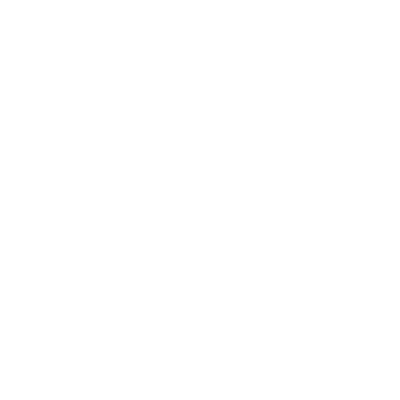
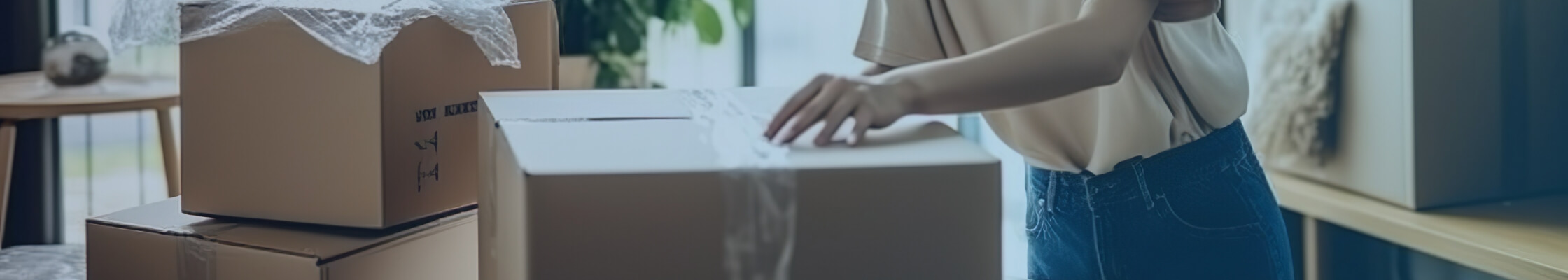
-
-
柔軟な勤務制度
フレックスタイム制(コアタイムなし)や在宅勤務制度※などを活用し家庭やプライベートとの両立を図りながら柔軟に働くことができます。また、月1回以上の年次有給休暇の取得を推奨しておりメリハリのある働き方を支援しています。
※在宅勤務の実施状況は勤務場所や各職場によって異なります。 -
転勤猶予制度
勤続3年目以上の総合職社員を対象に、育児や介護、配偶者の仕事、子の進学など会社が定める特定の事由について本人が申請し会社が認めた場合に一定期間転勤を猶予する制度です。
-
PICK UP.05
福利厚生
カフェテリアプラン
利用者が自己啓発や育児、介護、旅行などさまざまなメニューの中から任意のサービスを選び、会社に申請することでポイント分の補助が受けられる制度です。当社は年間650ポイント(6万5千円分)を毎年付与しています。
寮・社宅制度
各事業所の近くには寮・社宅を保有しており、住環境が整っています。寮での交流を通して、先輩や同期と交流を深めている社員もいます。
寮費は月々10,000円~12,000円程度(水道光熱費除く)で少ない個人負担で入居することが可能です。
寮は35歳まで、社宅は40歳まで入居することができます。
※寮のない事業所の場合は借り上げ寮となります。
■ PHOTO GALLERY
飯島寮(安来地区)
和彊寮NEO(熊谷地区)
南静寮(日立地区)
-

外観
-

部屋
-

食堂
※設備・部屋の間取りは寮により異なります。
-

外観
-

部屋
-

食堂
※設備・部屋の間取りは寮により異なります。
-

外観
-

大浴場
※設備・部屋の間取りは寮により異なります。
